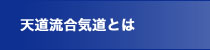合気道の歴史
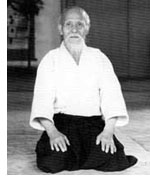 戦国時代(15世紀〜16世紀)の武士の闘争手段として発生・進化してきた様々な武術は、多くの優れた武術家たちの苦心によってさらに技術が高められ、また同時に高度な道徳的精神を備え、貴重な日本文化のひとつとして現代に伝えられてきた。
戦国時代(15世紀〜16世紀)の武士の闘争手段として発生・進化してきた様々な武術は、多くの優れた武術家たちの苦心によってさらに技術が高められ、また同時に高度な道徳的精神を備え、貴重な日本文化のひとつとして現代に伝えられてきた。
この優れた日本武術のひとつである「合気道」は、その源流を「大東流合気柔術」に見ることが出来る。大東流合気柔術は、源家より会津藩に伝えられ、会津藩内の五百石以上の藩士にのみ伝授された門外不出の極秘武道であった。
合気道開祖・植芝盛平翁(明治16(1883)年〜昭和44(1969)年)は、大正4(1915)年、元会津藩士、大東流合気柔術総本部長・武田惣角師に入門してこれを修め、その後他の武術の優れた面をも加え、さらに充実した武術(合気武道)として合気道を創始。昭和23(1948)年から「合気道」の名称を用いたものである。
天道流合気道とは
 清水健二は、12歳より柔道を始め、大学卒業後、合気道開祖・植芝盛平翁に入門。「最後の内弟子」として、1963年入門を許される。既に柔道四段にして基礎体力の出来ていた清水は、開祖の「受け」を取ることを中心に厳しい修業を重ね、短期の内に高段位八段を許される。
清水健二は、12歳より柔道を始め、大学卒業後、合気道開祖・植芝盛平翁に入門。「最後の内弟子」として、1963年入門を許される。既に柔道四段にして基礎体力の出来ていた清水は、開祖の「受け」を取ることを中心に厳しい修業を重ね、短期の内に高段位八段を許される。
開祖没後の昭和45(1970)年、「清水道場」として独立。5年後、「天道館」と改名。
昭和53(1978)年、西ドイツ(現ドイツ)へ招聘され、以後毎年ヨーロッパ各地へ合気道の指導を継続している。
昭和57(1982)年、『天道流』を掲げ、天道流合気道「天道館」となった。
天道流合気道は、開祖の創始された合気道の神髄をそのまま受け継ぐ合気道であり、開祖の気力の偉大さとその技を後世に伝え残そうとする、清水健二の合気道である。
※ この項に関する清水管長の逸話が、かわら版 76号「開祖と山本さん」に掲載されています。ご参照ください。
天道流合気道の理念
「天道」とは天の道であり、天の道理である。
「天道」とは誠でなければならず、その誠を人の道にあらわすところに、人間の修養がある。
天道流合気道では、この「天道」の精神をその根本の教えとしている。
他人に勝つのではなく、「己に克つ」ことを修道の心がまえとし、天道を自らのものにするため、誠の心をもって朝鍛夕錬しなければならない。誠の心とは不断に稽古を継続する精神であり、克己の精神こそが、天道流合気道の修道の根本である。
●上記は、東京大学名誉教授・文学博士 故 鎌田茂雄先生と清水健二管長との共著『禅と合気道』(人文書院)からの抜粋を元に、当サイトを制作・運営する天道館広報委員会がまとめたものを、清水管長が監修したものです。
 |
『禅と合気道』 著者:鎌田茂雄・清水健二/発行所:人文書院/価格:定価1,648円(本体1,600円) |
また、写真集『AIKIDO 天道』/著者:清水健二/発行所:クインエッセンス出版/価格:5,800円(本体5,631円)にも、鎌田先生、清水管長のお話しや、開祖・植芝盛平翁の言葉などが出ておりますので、ご参照ください。
![]()
※当ページに記載の文言は著作権に抵触しますので、一切の転載・転用・リンク等を禁止します。